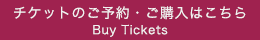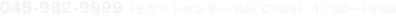佐藤俊介(ヴァイオリン)
出演日:2017年7月1日(土)14:00
Saturday 01 July 2017 , 14:00
作曲家の生きた時代を現代に位置づける試み。
ロマン派の時代の「主観的な音楽」という意味では、まだまだ取り組むものがあると思います。まだモダン楽器の演奏では、全然楽器などは無関係で、時代背景とか現代の解釈を疑う必要はないと思われています。この時代の音楽に対する価値観に対して、ちょっと疑いをかけたいと思っています。特定の作曲家というよりは、楽器そのものもピアノのタイプが色々ありますし、まだまだ、やることは沢山残っていると思います。ロマン派のこの時代の「主観的な音楽」という意味では、まだまだ取り組むものがあると思います。
バロック作品はその時代の楽器で演奏するコンサートも増えてきましたが、ロマン派の楽曲を当時の楽器で、というのは本当にまだ数が少ないですね。
佐藤:今回使うシュトライヒャーのピアノですが、実は僕自身、まだこの楽器に出会っていないんです。このあたりの時代の楽器は、出逢うことがなかなか難しいんです。
というのは、チェンバロなどは製作者がいますが、シュトライヒャーは6オクターブ以上のもっと大きいピアノです。19世紀後半あたりになってくると、ピアノは一人の製作者が作るには中途半端に大きくて、でも工場化して沢山作るほどは売れない。そうなると、100年以上前のもので状態のいい、メカニズムなども全部無事な楽器には出会えることが少ないんです。今回の楽器は、鈴木秀美さんが2015年11月にブラームスのプロジェクトをなさった時に、どこからかこのピアノのことを知って使われて、とにかく素晴らしい楽器だということを仰っていたので、彼のセンスを信じてこの楽器になっています。
この時代の楽器が今と何が違うかというと、一番分かりやすいところで、音量対音色のバランスがだいぶ変わるんです。ソフトなのですが、その分いろんな音色が、楽器そのものが主張してくる。やはりまずピアノの音色が柱にあって、それにどう対応していくかというのが弦楽器の仕事ですが、そうすると音楽作りも自動的に変わるものがあります。音量以外の沢山の色を使える。具体的にどうかは、実際にそのピアノと出会ってリハーサルして決めて出来上がっていくものだと思うのですが、すごくイマジネーションが広がるような感じですね。
今の大体のピアノ…例えばヤマハ、スタインウェイ、ベーゼンドルファーの音色は、やはり違うところより似ているところのほうが多いです。でもまだ、この時代のピアノというのは、ウィーン式とか、イギリス式とか、いろんな作り方がありました。国、時代、好みによって、3台並べると、3台全く違う音がして、なかなか比べられません。音域も、形も、ハンマーのメカニズムも違います。演奏者としても、スタインウェイだからこういう音だ、と事前にあまり想定できません。実際その楽器に出会って「あ、こういう楽器だからこういう風に変えていかなければいけないんだ」というのがあるので、予測できないのが楽しみというか…。
フィリアホールの公演では、全てほぼ同時期に作曲された作品が取り上げられます。ゲリット・ヤン・ファン・アイケンの作品はシューマンのヴァイオリン・ソナタとほぼ同じ時期に作曲されています。グリーグだけが少しだけ後ですが、ほぼ1850年代から60年代までで作曲されているものにスポットをあてて選ばれた理由を教えてください。
佐藤:ゲリット・ヤン・ファン・アイケンの作品に出会って弾いてみた時に、これは名作だな!と思いました。そこからこの人は一体どういう人だったのかと調べたら、ライプツィヒに勉強しに行って、シューマンとも交流があって。このプログラムは「ライプツィヒ」が作曲家たちの共通点です。ライプツィヒは音楽的に大変重要な場所だったので、そこから自然に色々と出てきたのですが、一番知られていないファン・アイケンが出発点だったんです。日本ではそれこそ弾かれたことは無いのでは?ひょっとしたら日本初演でしょうか?(笑)
意外にこの(ロマン派の)時代、オランダ出身の作曲家はいまして、殆どの場合はドイツに行って勉強して、というのが多いのですが、なかなかいい作品を書いているんですね。次はオランダ中心のプログラムというのもできるくらいですが、一方クララ・シューマンというのもなかなか耳にすることもないなと思いまして。
アイケンとシューマンにはやはり交流があったということは、必然的にクララ(・シューマン)とも交流があったと。グリーグもそこに入ってくるのでしょうか?
佐藤:グリーグはシューマンと直接の交流は無かったのですが、ライプツィヒに留学しに行っています。実を言いますとそこでは鬱病になってしまったようで、幸せな時期だとは言えないらしいですが…。
以前フィリアホールにご出演頂いた時には佐藤卓史さんとグリーグのヴァイオリン・ソナタを全曲演奏されました。その時の思い入れもあられるのかなと思っていましたが。
佐藤:それとはまた違う、まったく新しい関心ですね。まさかヒストリカルピアノと演奏するとは夢にも思っていなかったです(笑)。
シューマンも、まだヒストリカルな楽器で弾かれることは少ないですね。
佐藤:ヒストリカルな楽器で弾く、ということだけならあると思うのですが、演奏スタイル的にはまだまだですね。たとえば具体的には、「テンポを揺らす」というのはやはりまだタブーだと思うんです。まだ枠から外れないというか。客観的にテンポを守る。主観的にしてしまうなら、ここはすごい好きだから、とか、ここは興奮の場面だからもっと急ぐ、とかありますが、そういう感情を前にもってきて演奏するというアプローチは、まだあまり聴いていないですね。
シューマンの曲だとそういうものがむしろあてはまりやすそうです。溢れ出るものが抑えきれず、何とか形に収めようととしているようなタイプの作曲家だと思うので、そうしたアプローチはむしろしっくりきそうな予感がしています。
佐藤:実は2番のソナタは初めて弾くんです。1番は弾いたことがあるんですけれど。
激しい曲ですが、そこを何とか構築させようという意思を感じる、そのバランスが魅力的な曲ですよね。佐藤さんはバロックならバロック、ロマン派ならロマン派、近現代なら近現代と色々なレパートリーをお持ちですが、それぞれの時代で共通して意識していることはなにかありますか。
佐藤:作曲家たち自身が人間であった、ということは意識しています。失望したり、成功があったり、お金が無かったり、失恋したり…。もちろん、それが作品そのものにどれだけ関係してくるかということはまったく別問題ですが。
バッハのカンタータなどは、これを書いた時の心境はどうだったのかということはほぼ無関係だと思います。でも一方でバッハならいつも思うことは、どうやって子どもがあんなにたくさんいながら、毎週カンタータを書き、しかも教え子もいて、一日の時間の配分が一体どうなっていたのか?と。そこがすごく惹かれます。人間としてどうであったかという。バッハだって色々不満があったわけですし。ライプツィヒのトーマス教会での音楽隊の人数が足りない、こんな小編成のオケじゃ何も出来ない、としょっちゅう手紙を書いているんですよね。そういうふうに考え直すと、一気に分かりやすくなる。距離が近くなるだけでなくて、会って話せば自然と分かりあえるようなものが出てくるんですよね。ですから、そこを忘れてはいけないと思います。いくら年月が経って偉大な曲だからといって、一人の人間がその曲を書いているわけですから。そういう意味では、時代によって意識を変える、というのはあまり無いですね。
どちらかというと作曲家のことを知ることが、必然的にそういった綿密な分析につながり、奏法や楽器のことまで考えていくことに結果的につながっていく、という考え方でしょうか。
佐藤:ある意味、新しい世界に行って何を吸収できるか、自分の時代に何を持って帰るかという、時間旅行ですね。あと、作曲家の心境がどうだったかということが、作曲家によって違うというか。たとえばバッハのカンタータの場合だったら、自分の持っていた感情というよりは、たまたま日曜日の聖書からのテーマに基づいて作曲していて、その聖書を読み直すと、こういう音楽とのつながりがあるんだとか、本当に作曲家ごとに違います。曲ごとにも違います。ですから、毎回毎回白紙に戻しています。経験を積み重ねていけば勘で分かるものというものももちろん出てきますが、基本的には何も知らないというところをベースラインにして始めたいと思っています。
今回は前日6月30日に浜離宮朝日ホールで、鈴木秀美さんを迎えてオール・ブラームス・プログラムにも取組まれます。2公演ともロマン派の作曲家ですが、このあたりの作曲家、あるいは時代で、他に取り組んでいきたいという領域はありますか?
佐藤:特定の作曲家というのはあまりないのですが、ロマン派のこの時代の「主観的な音楽」という意味では、まだまだ取り組むものがあると思います。「古楽」と呼ばれるようになってしまったものは、ある意味「別枠」に入っていて、それは全く別のやり方でOKとされる、承認される時代になりましたけど、まだモダン楽器の演奏では、全然楽器などは無関係で、時代背景とか現代の解釈を疑う必要はないと思われています。ですから、そういう意味で、この時代の音楽に対する価値観に対して、ちょっと疑いをかけたいと思っています。一般に多く弾かれているからこそ、本当にそうなんだろうか、もっと違うやり方はないのだろうか、と。特定の作曲家というよりは、楽器そのものもピアノのタイプが色々あるし、じゃあプレイエルで弾くフレンチのロマン派の曲はどうなのか?とか。まだまだ、やることは沢山残っていると思います。
今を疑う、ということですね。そうやって疑いをかけていった活動が、結果「現在」の歴史に組み込まれていくのがまた面白いですね。
佐藤:そうですよね、これがまた100年経てば。
それが流行していた時代だったんだ、と、50年くらいするとこの時代はロマン派のものを当時の楽器で再演する演奏が多かった、と語られるようになるのかも知れないですね。
佐藤:あと面白いことは、この時代と今の時代が決定的に違う点として、ブラームスやシューマンの時代では、まだコンテンポラリーなもの、同世代・同時代の他の作曲家たちのものを演奏するのが普通だったわけです。ですから、目線は絶えず「今」だったわけです。たとえばメンデルスゾーンがバッハの「マタイ受難曲」を再発掘した時に何をしたかというと、そのまま演奏するのではなく、当時の編成やスタイルにちょっと書き直して、それをバッハだ、という風に世の中に伝えた訳です。ですから「今」というものがすごく大事だった時代なんですね。それが2000年代になると、コンテンポラリー・ミュージックというのは全く別な枠になっていて、そこが根本的に違うところですよね。演奏者自身は作曲することはあまりないですし。
作曲家は演奏家ですもんね。特にこのブラームスとかシューマンの時代は、友人の曲を弾くという感じですよね。
佐藤:お互いの曲を弾いて、更に弾くだけでなくて、自分のなにか数小節加えちゃったりとか、書き替えたりとか、もうちょっと華やかにしよう!とか、そういうのが自由に扱われていた。今ではちょっと考えられない、想像がなかなかつかない状況ですよね。
ショパンなどは、最近当時の楽器で弾くというのが多くなってきました。先日もフィリアホールでは仲道郁代さんが所蔵のプレイエルを持ち込んでショパンの曲を演奏し、その二日前には「デンハーグピアノ五重奏団」が、やはりグレーバーのピアノとシューベルトが当時使っていたであろう様式の編成・楽器で「ます」を演奏しました。
佐藤:50年後はどうなっているんでしょうね。
グレーバーとプレイエルではもちろんピアノの様式が全然違います。フォルテピアノってこういう感じの音なのかな?と思っていても、やはり違うんですよね。古いものほど違う。ショパンでも、今のモダン・ピアノで大きい音量でパワフルに弾く楽曲、たとえば「革命のエチュード」などをフォルテピアノで聴くと、いかに当時のピアノの許容範囲を超えそうな激しい書かれ方をされていたか、ということが分かってしまうんですよね。
佐藤:ベートーヴェンなんかまさにそうです。楽器の限界に到達して、そこから出る摩擦というものがあるからエキサイティングだというのが分かってきます。先日彩の国で演奏したクラリネットとの演奏も、高音を使いましたが、たとえば「春の祭典」とかのファゴットなどの管楽器の高音は、非常に出しにくい、もしくはあまり美しい音ではない、というのが、むしろ要求される色だったわけですよね。「苦痛」であった音が今の楽器だと、ほんの70年、80年で変わってしまって簡単に出せるようになって、頑張ってギリギリ出す、という音色は失われてしまった。70年、80年前の音楽でさえ聴こえてくるものですが、それより前のベートーヴェンなどは本当にピアノを叩き潰しながら弾いていたと思いますが、そこのぶつかりが楽しいんです。
それでは改めて、お客様へのメッセージをお願いいたします。
佐藤:今回はドイツのライプツィヒを接点とした4人の作曲家たちの曲を演奏します。ライプツィヒといいますと色々な作曲家が思い浮かびますが、その中から4人の作曲家、ロベルト・シューマン、シューマンの妻であったクララ・シューマン、ノルウェー人のグリーグ、そして最後にオランダ人のゲリット・ヤン・ファン・アイケンという、あまり知られていない作曲家なのですが、彼はオランダからライプツィヒに留学してそこで素晴らしいソナタを一曲書いています。このファン・アイケンのソナタを弾くのはおそらく日本初演となるコンサートです。最後にフィリアホールで弾かせて頂いたのは2007年で、10年ぶりのコンサートとなりますので、大変楽しみにしています。7月1日、どうぞお越しください。
(取材協力:KAJIMOTO、朝日新聞社)