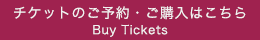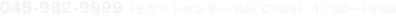近藤嘉宏 (ピアノ)
出演日:2017年9月10日(日)15:00
Sunday 10 September 2017 , 15:00
現在に蘇る作曲者/ピアニスト・リストの奥深さ。
リストのオペラ・パラフレーズ作品は「オペラを借りていながら超えている」という自信と、それだけの表現ができるという表現力、作曲力が満ちています。単なる目くらましや、びっくりさせるだけの作品ではなくて、音楽としての感動があります。「ノルマの回想」は大曲ですが、色んな所からあれだけ借りてきて、自分の構成で一曲にきっちり作っていながら何の遜色もない、ソナタを聴いているような曲が成り立っている構成力。そこがリストの凄さであり、魅力であると思います。ただひけらかすだけの作品ではない!というのが、聴いていただけるとわかるのではないかと思います。
―今回はベヒシュタイン・ピアノでの演奏になります。どのような楽器なのでしょうか?
ピアノのストラディバリウスと称されるほどの楽器でありながら、第二次世界大戦直後、独裁者が愛した楽器という括りで敬遠され、非常に不遇の時代を歩んだピアノですが、それが20世紀末頃から少しずつ復興の動きが出てきました。2000年に入ってから更に改良が進み、次第に楽器が良くなってきて、昔の響きを残しつつ、スタインウェイのようなスケールを持ち、以前の小ぢんまりした印象が払拭された、非常に良い楽器になりました。
―ベヒシュタインの音を聴いたことがない方も多いであろう中、非常に楽しみなコンサートになるかと思います。
去年(2016年)、ミュンヘンでのリサイタルで、この新しいベヒシュタインで演奏しました。お城の中のホールなので、殆どのコンサートが持ち込みのピアノによる演奏なのですが、ベーゼンドルファーかスタインウェイしか選択肢がない雰囲気の中でベヒシュタインはどうか、と持ちかけてみたところ、持込みできるということで、一番新しい型のピアノで演奏してみました。お客さんはもちろん、裏で聴いていたスタッフの方たちも「凄いピアノだね!」と上々の評判でした。この時は今回も演奏するリストの「ノルマの回想」を弾きました。それと、ショパンとベートーヴェンを演奏しました。
―リストはベヒシュタインを賞賛していましたね。
ベヒシュタインは音の立ち上がりがとてつもなく良く、分解性があります。音が重なり合った途端、それぞれの声部の動きの分解能の良さがちゃんと音として機能する。それぞれの音の繋がりが横に全部あって、構成音として意味があって、丁度いい響きがあって。そういう意味での厚みがちゃんとあって聴こえてくるのです。
―スケールの大きさと成分の分離性の両立出来る楽器はそれほどないのですね。
そうなんです。ベヒシュタインの良さってもう一つあって、ブリリアント(輝き)な要素をもっているんですよ。例えばベーゼンドルファーは華麗というよりは落ち着いた、ベートーヴェンとかシューベルトとか、そんな感じです。だけどもベヒシュタインは、ショパンも「いける」感じなんです。高音のキラキラした感じは非常にクリスタルなので、そこもベヒシュタインの魅力でもあるし、戦前凄く良く使われていたというのが理解できます。
これは余談になるのですが、去年、1880年代のベルリン・フィルの定期演奏会など、一年間のプログラムを手に入れたのですが、それによると、ピアノ協奏曲やヴァイオリン協奏曲などが必ず入っているんですが、作曲者自身をソリストと同じ感覚でゲストとして招いて、例えば一つのコンサートの中の、前半の最後の方だけ自作を振らせるということを当時やっていたようです。それ以外の楽曲は基本的にはハンス・フォン・ビューローが指揮していたんですが、例えばグリーグが呼ばれたり、ブラームスが呼ばれて指揮をして、ピアノはハンス・フォン・ビューローが弾いて…というのがあったりするんです。そして、そこで使われるピアノはやっぱり全部ベヒシュタインなんです。大きく書いてある。どのコンサートでも、ピアノ協奏曲の時は全部ベヒシュタイン。要するに、当時は普通に使われていた楽器なんです。今では全世界がスタインウェイになっていますが―当時もアメリカでは使われていたと思いますが―、ヨーロッパに行くとやっぱりベヒシュタインが強くって、そういう住み分けがされていた。一方でオーストリアだったらベーゼンドルファー、というように、そういう色々なピアノを知ると、どこの楽器も素晴らしいので、それぞれの魅力を感じていただけたらというのもあります。やっぱり僕の好きな楽器でもあるので、弾く機会があれば弾かせて頂くようにしているんですよ。
―近藤さんから見た、今回の「ベヒシュタイン」と「リスト」という組み合わせによるリサイタルの魅力、聴きどころを教えて下さい。
リストというと、「愛の夢」や「ラ・カンパネラ」などの有名な曲があり、一方で「巡礼の年」や「オーベルマンの谷」など―もちろんその他がそうではないという意味ではないのですが―どちらかというと「アカデミックな」方向で捉えられている曲があります。でも、本当はそのような区分けを越えている作品もあります。たとえばオペラのパラフレーズなどは、そこにリスト自身の作曲や音楽表現や楽曲構成のテクニック全てを網羅して、オペラというものを上手く要素を借りて、リストが「自分の」作品を作ってしまっている…というところが凄いところです。それはもう借り物ではなく、リスト自身の理念というか非常に内容の深い世界が展開されているんです。
今回のプログラムは実際にリスト自身が演奏していた曲で構成されているのですが、そういうところをリスト自身も気に入っていたようで、リストが好んで演奏していた曲は「ソナタ」や「オーベルマン」ではなくて、圧倒的にパラフレーズが多い。そこにリストの自信や思い入れなどが見て取れると思います。それが弾いていくと解ってくるんです。オペラを超えている、借りていながら自分の作品を作っているプレゼンテーション、というか、「オペラを借りていながら超えている」という自信と、それだけの表現ができるという表現力、作曲力。それを誇りにしている。単なる目くらましや、びっくりさせるだけの作品ではなくて、音楽としての感動があります。見過ごされがちですが、ソナタなどと匹敵する音楽的な内容の深さが見て取れる。
「ノルマの回想」は大曲ですが、色んな所からあれだけ借りてきて、自分の構成で一曲にきっちり作っていながら何の遜色もない、ソナタを聴いているような曲が成り立っている構成力。そこがリストの凄さであり、魅力であると思います。実際のメインは「ノルマ」ですね(笑)。今回は「ルチア」「清教徒」のパラフレーズなども演奏しますが、ショパンのようだったり、曲調としては面白いものもあるんですが、ただひけらかすだけの作品ではない!というのが、今回のコンサートのパラフレーズを聴いていただけるとわかるのではないかと思います。
―今回はプログラムの中に、リストが実際に弾いたショパンの曲も入っていますね。
ええ、マズルカが一曲だけ。リストとショパンというのは同じ時代に生きたということもあり、リストのおかげで今のショパンがあるというか…リストは人生の後半は教育者としているわけですが、非常に沢山のお弟子さんにショパンの曲を教材として使っていて、ショパンをものすごく評価して広めていった経緯があるんです。浦久俊彦さん(作家・プロデューサー)が、リストが書いたショパンについての本のオリジナルを持っていると仰っていたけれど、リストとショパンの間柄というのはそういったところからも解ってくるかと。
―実際にショパンが聞いていたときに、リストがショパンを弾いていたらどうだっただろうかと考えると面白いですね。
今回はリスト・プログラムというコンセプトで、殆どがリストの曲の中、ショパンを入れたのはそういった意味もあります。
―ピアニストの立場として、リストの曲を演奏するというのはどういった感じでしょうか。他の作曲家とどう違うのか、などをお伺いしたいと思います。
リストというのは、凄く自分自身が弾けた人なので、ものすごく難しいんですが、テクニックが合理的なんです。最低限の難しさで最高の効果をあげる、ということが出来ている。その上で難しいのですが、そういうテクニックのコストパフォーマンスが非常に高いですね。多分、ベートーヴェンやブラームスとか他の作曲家と比べて段違いに熟知しているというか、相当良く弾けたんだろうな…というのがそこからわかるんです。ラフマニノフなんかも難しいのですが、如何せんラフマニノフは手がめちゃめちゃ大きかったので、彼にとっては楽でも、他の人には届かないフィンガリングという、またちょっと違った難しさが出てくるんですが、リストは若干大きめとはいえそこまで巨大ではなかったのか、ラフマニノフに比べるとそのあたりが合理的で、難しいのですが報われる。表現なんかもいいところに、そうだよね、そのとおりだよね!という腑に落ちることがいっぱい音楽的に表現されていて、同意しながら弾けるのが、共感したりシンパシーを感じる部分でもあります。
―作曲家として、またピアニストとして、リストというのは近藤さんとしてどういった存在ですか?
ピアニストとしては、多分、それまでの歴史の中で初めて所謂現代的な奏法で弾いた人です。しかも、今の名だたるピアニストと遜色がないくらい弾けたであろうことが、曲から推測できる。作曲家としてはベートーヴェンとかバッハとかモーツァルトとか、正統的な昔からの伝統を引き継ぎつつ、彼の生きた七十数年の中で、それこそ無調の作品も書いてるわけですし、一気に音楽史の歴史を70年どころではない、その倍くらい進めた。彼が居たからこそ、ワーグナーをはじめ、シェーンベルクもそうですし、ショスタコーヴィチもリストがいたから存在できるのだろうと。リストが居なかったら、音楽はそこまで進んだだろうか?と。だから作曲家としても、もの凄く多彩で、もの凄くキャパシティの広い人なんだろうなと相当もの凄い才能の人だったんだろうな、と。
ピアノの音域もリストの時代に段々広がってきて、やっぱり今までの楽器では表現不足だと、無理だと、どんどんどんどん改良が重ねられていって今のピアノが出来ました。それこそワーグナーの音楽だってライトモティーフなどの形があるけれど、リストのソナタなどを見ると、ライトモティーフのようなものは出てきているので、やはり色んな意味で先を行っています。
―たとえばロ短調ソナタは、何回聴いても「新しい」曲ですね。
そうなんです!毎回ちょっと聴くところを変えるだけで、違う曲に聴こえてくるんですよ。それが、聴く側にとっても重層的な聴き方ができるというか。そこが薄っぺらいものだと一辺倒な聴き方しかできないのですが、厚みのある作品ということになると、どこから聴いても違うものが見えて、コンビネーションもあるし、全然違うんですよね。やっぱりリストはそういうことを色々試していったんだろうなと。その新しいものを作っていく中で、パラフレーズというものもあって、そこにむしろソナタ的な要素を組み込んできてるところが面白いです。オペラという娯楽の極みに、凄く哲学的な表現の要素を見込んだりしているところに、非常にインテリジェンスな音楽になる。ああいうパラフレーズって未だに…出来ないですよね。そこに魅力を感じます。もちろん演奏効果もあるんですが、あれだけ考えられていて深いというか、そういうものっていうのはあれ以降もないですよね。「ドン・ジョヴァンニ」(の回想)などをやってみても、普通は中々まとまらないもので、色々何となくあちこち借りてきたものの最後はチャンチャン、になってしまいがちなのが、彼の場合は違いますからね。次に何が出てくる?と期待させられて、あれがああ、ここに繋がるのか!って、関連性を持たせながら一気に聴き手を惹きつけていって、最後に充実感を持たせる。ぜんぜん違うタイプなんですよね、単なるパラフレーズではない、作曲家としてのその巨大さ。ベートーヴェンも巨大ですけれど、才能という面で言えば、リストの方が有り余ってしまっていたかも。
―本当にそのオペラ作品に真剣に向き合って、この作品をどうやったら魅力的に聴かせられるかというところを研究して作曲したのでしょうね。
だから本当に「生きて」というか、原曲以上に、アレ、こんなに面白い所だったっけこのフレーズ、となるんです。「ノルマ」なんて、本当に一番キャッチーな所を使っていないんです。これって確かにあったけど、そんなに良いところだったっけ?みたいな所をもってきているんですが、とても魅力的なんですよ。ですからそれが、リストからしたら「イヤイヤここはもっと魅力的になるぜ」、「泣かせてやるぜここで」みたいな、そういうチャレンジャー的なところも感じます。でも、ビッグマウスで嫌な感じがするんじゃないんですよね。作品に関しては凄く真摯に向き合っているので、自信は凄く感じるんだけど、謙虚な部分もあるんです。その謙虚さが、リストの魅力なのかな。
―お話は変わって…近藤さんがピアノを始めたきっかけを教えて下さい。
生まれは川崎ですが、その後、札幌に引っ越しました。その頃4歳くらいだったのですが、アップライトのピアノが家にあって、特に興味があったわけではないのですが、姉が始めたのをきっかけに自分もやらせて欲しいと言ったそうです。
小2の頃に、関西を経て川崎に戻ってきたのですが、関西に居たときに生まれて初めて聴きに行ったピアニスト、アダム・ハラシェビッチのコンサートで、彼が、子供の僕にも分かる位、たまたまとても演奏の調子が悪くて…これなら僕にもピアニストになれるんじゃないか…?と思ったんです。それがきっかけで、川崎に戻ってきた後、桐朋の音楽教室に通ったのですが、そのハラシェビッチの「威力」が長持ちしたのです。今だとハラシェビッチは結構好きなんですよ。ショパンのレコードなど、どれも凄く良いんです。奇を衒わない演奏で。なのに、何であの時あんな演奏だったのかな?というのが、今でも不思議ですね。
―その後色々と勉強されて、ミュンヘンでゲルハルト・オピッツに師事されました。
日本音楽コンクールで初めて賞を頂いた翌年の大学2年生頃に、大学に教授としていらしていたオピッツ先生の公開レッスンを受けたのですが、それまでも(ヴラド・)ペルルミュテール氏などのレッスンを受けてきて、この先どうしようかな…と思っていました。今でもそうなんですが、ショパンを突き詰めたいと思っていたんですが、でもちょっとまてよ、ベートーヴェンの伝統だったりセオリー、構成などをきっちり勉強しておかないとダメだな、という思いもあり、オピッツ先生の演奏家としてのプレゼンテーションからも学べるんじゃないかと思いました。
オピッツ先生はあまり多くを語らないのですが、核の部分で基本的に必要なことを的確にしてくれたり、インスピレーションを下さる、そんなレッスンをして下さる方でした。隣で弾いて指導してくれるので、言葉というより演奏で示して頂いたり、そこから身に入ってくることが多かったように思います。先生は今60に入った頃だと思うのですが、年齢を重ねられてより、音の密度が濃くなってきて、奇をてらわない、素朴な語り口の中に音一つ一つの色合い、意味合い、表現の色彩感、ニュアンスが素晴らしい方ですよね。そこが僕の目標でもあります。
小さい頃から、僕はアルトゥール・ルービンシュタインが好きだったんです。ルービンシュタインは、変なことを一切しないのに、個性がしっかりある。なにかしなくても個性はできる、というのは一つの理想です。何かしないでも色んな表現、ニュアンスでもって自分の個性っていうのはいくらでも強められる。そういうことで自分を表現したり、突き詰めていったりできる。大学の時からそこを課題にしていたけれども、若いときは引き出しが少ない、そうすると演奏を揺らしたりとか、どうしても形で訴えようとしてしまう。わざとらしく表現したくなりがちです。そういう自分に自制をかけてやらないようにしてきたけれど、それで単調になってしまったり。
ピアノの音に関しては、ルービンシュタインと、ミュンヘンで聞いた(アルトゥーロ・ベネディッティ・)ミケランジェリの音が未だに理想として残っています。あのピアノの調整を求めて、ピアノにも詳しくならなければと、ピアノを買うにしても、調律師にしても、ベヒシュタインなら、スタインウェイなら…というように、お互いに議論しながらピアノに関してはどう調整してくか色々突き詰めていって、やっと答えが10何年掛かりましたが、一つの形、モデルが、音と調律が形作られてきています。不思議なのはそれをやると、ベヒシュタインもスタンウェイも同じような音がするようになるんです。同じ方向を向いて、方向性が同じだから。
―近藤さんにとって、ピアノとはどういう存在ですか?
以前は思わなかったんですが、今となって、言葉以上に自分や色々なことを表現できる楽器であると思いますね。自分が思っていること、感じていること、それを言葉以上の世界観、ニュアンスとかで表現できると、数年前から感じるようになりました。というのはやっぱり、僕自身の引き出しが増えてきたんだろうなと思うんですよ。
僕が思うのは、音楽は言葉を超える表現が可能になるわけですが、例えばそれを人に説明するという時があるわけです。その時に、どれだけそこに言葉で近づけるかということも、非常に重要なんじゃないかなと。その時に僕が思うのは、奇想天外な比喩とかの方が伝わりやすかったりするんです。普通に説明すると意外に解らない、でも突拍子な例えの方がなるほど!っていう伝わり方をしたりします。どうやって今度は言葉に変換して、ある種、理論として言葉から理解してもらおうかな、ということも、僕は大事にしたいなとは思っています。言葉というところから入ってくることによって、何かのインスピレーションを聴き手が感じて、読み手が感じて、それを前提として音楽を聴くと、そこで初めて解るケースもあると思うんです。その導きと導入があって、あ、解った!というスイッチが入る。だから、言葉で音楽の表現について出来るだけ近づいていくというのも、凄く大切だと思います。
注意して耳を傾けてみると、そこから入ってくることがあるわけです。だから、どうやって言葉でそこの良さを説明するかというか、音楽的な細かい機微をどういう風に言葉で表現できるか…それが、ある時は突拍子もない言葉の比喩であるかもしれないけど、そこに何かのインスピレーションがあれば、人間て突拍子もない方が、ひらめきってあったりするんですよね。だからそこらへんは大事にしたいなと思っているんですよね。僕は言葉とか理論的に行く傾向があるんです。その方法論でいくと、あまりに理論で行き過ぎると、面白くなくなっていってしまう。だからそこは凄く気をつけています。練習の時は、とにかくより細かく詰めていくんですよ。そこでとにかく精緻なものを作っておいて、本番は全部解き放つんです。頭の中に雛形というものは叩き込むわけです。でもその雛形通りに演奏したってつまんないから、ある程度、細かいディティールまで自分の中に叩き込めれば、物凄く明瞭・明確に音楽が見える。その上で、ブワっとぼかしを入れる。そうすると、とんでもない形崩れは起こさないわけなんですよね。演奏の形が崩れることは怖いわけです。訳のわからない、抑制の効かない、全くの支離滅裂に陥るというのが音楽の怖いところ。だからそういう細かいところまで見通してあれば、本番、あとはそんな、本能的に一線を超える越えないが解る。それは細かいところをやっていればやっているほど、その線引きは明確にわかるんですよ。ここは越えちゃいけない、ここは遊べるな、というのが感覚的に。そのボーダーを明確にするためにも、より細かく作っておくことが必要かなと、そういう考え方でやっています。
だから本番は僕の中では一番遊べるんですよ。練習の時はあそこの部分、ここの部分て全部考えてやらなきゃいけない。でも本番では考えなくて済む、一番気持ちが解き放たれるのが嬉しい。一見、本番は練習してきたのが全部無駄になっちゃうんじゃないかという風に思う方もいるかもしれない、でもそうじゃなくて、細かいこと全部やってきたことが解き放つから、意味があるというか。そのためにやっているんだと。本番自由に弾く為のた、普段は足枷であるし、そうなればなるほど、プラスアルファ他にも色々良いことがあって、音楽が凄く新鮮なんですよ。あれだけ何回も弾いているから普通飽きるだろうと。でも飽きないんですよね。自由に弾くから。水を得た魚になれるというか、なんかそれがふっと弾いていたときに見えてくることがある。それがまた良さですよね。
―それでは最後に、フィリアホールのお客様にメッセージをお願いします。
以前出演したのはもう十数年前になると思いますが…。本当に久しぶりなんですけれど、元々地元が川崎、新百合ヶ丘と近いので、フィリアホールはある種実家というか、地元というか…。そういう親しみもあるんですけれど、青葉台にはおいしいラーメン屋さんがあったんですよね。学生の時から青葉台に行くときには必ず寄ってたんです。学生の時といえばもう、20年も前になってしまうので、もうそのラーメン屋さんは閉じちゃったみたいで。でもその息子さんが、今はよみうりランドの方で営業しているらしいんです。それを先日友達と話していて、懐かしいなぁ、なんて言ってたんです。フィリアホールは久しぶりで本当に僕は楽しみにしていて。でも十何年のインターバルがあっての再度出演させていただく、再登場させていただくありがたさもありますし。また新しいスタートなのかな、という気もしています。