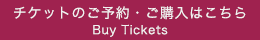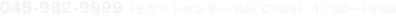クリストフ・プレガルディエン (テノール)
出演日:2014年2月14日(金)19:00
Friday 14 February 2014 , 19:00
無添加のテノール、因習しらずのピアノ
音楽評論家の舩木篤也氏のエッセイを掲載。
――これまで多くの人々に、繰りかえし歌い継がれてきた《冬の旅》。
この期に及んで鮮度を保つとすれば、ときに水と油の関係にあるこんな二人に演ってもらうほかあるまい。楽しみにしたい。――
■■■歌の力、ことばの力■■■
もっとも、歌が分かるということは、そう単純なことではない。ただ、少なくとも、それが「意味」を把握することと同義でないのは確かであろう。音声言語のもつ力は――字幕や翻訳で示されるような――意味表示にだけ根ざしているわけではないのだから。
音声言語には、声の強弱や濃淡がともなう。あるいは、その言語に固有の子音や母音、声にならないノイズのようなものまであり、それらのせめぎ合いが常に生起している。さらには、ことばを発する人の表情や身ぶりも無視できない。声に出された言語とは、つまるところ、ことばのそうした情動面と、ことばの意味とが、たえず火花を散らして交わる戦場のようなものと言えそうだ。しかも、リートのことばは日常のことばとは異なる詩のことばである。そんな戦場をあえて過熱させることば、ということになる。そして歌とは、リートとは、そんな熱き戦いに対して作曲家の側から下すひとつの解釈であり、歌唱芸術とは、その解釈を解き明かす術のことにほかなるまい。
そこでプレガルディエンだが、彼の歌唱にあっては、こうした意味での「戦い」が、実にくっきりと見えてくるのだ。
■■■比類なきピュアな歌声■■■
まず大前提として、歌詞がすべて、文字を追わずとも耳で分かる。ドイツ人がドイツ語を歌うからといって、これは決して当たり前のことではなく、その明度は、あのディートリヒ・フィッシャー=ディースカウをさえ凌ぐと筆者は思っている。声楽の発声法に基づいているはずなのに、ふしぎと声楽臭がなく、その声は、自然に湧き出でる清水のよう。ときに、ナレーションに接しているのでは?と錯覚するほどだ。声楽臭がないのは、歌い手の側から加えられるいわば情動の添加物が、極力排されている証拠だろう。かくして作曲家の側から詩に下した解釈そのものが、限りなくピュアに伝わってくる。彼が舞台上でみせる顔の表情や身ぶりがきわめて厳選されているのも、これと連動しているのだ。
こうしたピュアネスがあればこそ、情動と意味の火花を散らす戦いが、こちらの心身にぐっと迫ってくる。かりに聴き手が当該言語に明るくなくともである。先に「よく分かる歌」としたゆえんだ。御年58になるヴェテラン、プレガルディエン。彼は一般にリリック・テノールのタイプに分類されるようだが、ここではあえて「ピュア・テノール」と呼ぶことにしよう。
■■■天才ゲースのピアノ■■■
さて、このプレガルディエンにこのたび随行するピアニストが、ミヒャエル・ゲースである。フォルテピアノ奏者のアンドレアス・シュタイアーとならんで、プレガルディエンが最も頼りにし、最も頻繁に共演してきた人だ。リートの「伴奏」などという言い方がいまだ通っているところでは、リート・ピアニストはどうしてもコンサート・ピアニストに比べ低く見られ、注目されにくいだろうか。ゲースは、そうした中でもさらに知る人ぞ知るといった存在であろうが、筆者に言わせれば、リートを聴くのにいまこんなに面白いピアニストもない。プレガルディエンのときは特にそうだ。なぜならこの二人は――逆説的なようだが――ときに水と油の関係にあるとさえ思えるからである。
■■■シューベルトの現代性■■■
たとえば、ゲースが思わぬ音に思いもよらぬ強いアクセントを、それもちょっとタイミングをずらして置いたりする。ところがプレガルディエンはというと、われ関せず。あの透明な声を、透明なまますうっと発したりする。そんな場面をよく目撃したものだが、それによって気づかされるのだ。作曲家が記した歌のパートとピアノ・パートは、必ずしも調和を目指してはいないのだと。ほかでもない、シューベルトこそ、まさにそんな作曲家であって、両パートのあいだには亀裂が横たわっている場合すらある。ことばの表面的な意味と、そのことばを発している詩的主体の心の闇。それらふたつの相容れない矛盾。亀裂は、そんな矛盾を暗に表しているのかもしれない。そして《冬の旅》のような作品には、そうした亀裂が無数に走っていることだろう。氷のように冷たく、鋭い亀裂が――。
先にリート・ピアニストと言ったが、ゲースは本国ドイツでは、即興パフォーマーとして、あるいは作曲家としても活躍している。またリサイタルもよく催すのだが、名曲にしばしば自作も交えるそのプログラムは、調性や、文学的背景、あるいは特定の色といった、あるテーマのもとに束ねられたコンセプチュアルなものであり、商業ピアニストが組む因習的なものとは、やはり一線を画している。彼のリート演奏にたいする積極姿勢も、そうしたちょっとゲリラ的な活動の一環としてとらえるべきなのだろう。どうりで、あたりさわりのない「伴奏」から遠いわけである。
■■■不朽の名作《冬の旅》■■■
これまで多くの人々に、繰りかえし歌い継がれてきた《冬の旅》。この期に及んで鮮度を保つとすれば、こんな二人に演ってもらうほかあるまい。楽しみにしたい。