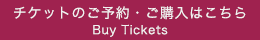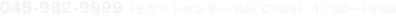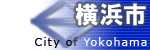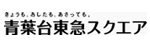五田詩朗 (打楽器)
出演日:2016年2月6日(土)13:00
Saturday 06 February 2016 , 13:00
こどもたちにこそ、本気の音楽を。
フィリアホールのような客席とステージの距離が近いホールで、もっと子どものためのプログラムを増やしていきたいです。また、地域の芸術施設が連携したプログラムにも、挑戦したいと考えています。芸術施設が連携して人々にメッセージを発信していくことで、芸術全体が、もっと人々の暮らしと近しいものとして存在する社会を夢見ています。
フィリアホールでは「よちよちおんがくワークショップ」「よちよち音楽教室」「ホール体験デー」などのご出演ですっかりおなじみですが、それ以前からも小さなお子さま向けのコンサートやワークショップに出演されてきました。こうした活動をフィリアホールで始めたきっかけはなんでしょうか?
もうずいぶん前になりますが、フィリアホールで開催されたファミリーコンサートに僕が出演した際に、僕の演奏する様子がたまたま当時の制作担当の方の目にとまり、進行中だった別の子ども向け音楽プログラムの企画に引き入れてくださったのが、僕とフィリアホールとのご縁の始まりです。
「よちよち」イベントで接するのは、多くのコンサートホールでは中に入ることができない小さなこどもたちです。彼らの多くがこのイベントで、生まれてはじめて西洋楽器に対するわけですが、フィリアホールで参加している子どもの反応はいかがですか?
初めての空間に最初は緊張気味の子どもたちも、フィリアホールの醸し出すやわらかい雰囲気に助けられ、すぐに安心して音楽に集中していきます。青葉台という土地柄もあるのかもしれませんが、フィリアホールにやってくる子どもたちの身体には、ゆったりとした時間が流れているように感じます。
多くの子どもたちにふれ、こちらが教わることも多いと思います。これまでの公演やイベントの中で、特に印象的なエピソードがあれば教えてください。
言うまでもないことですが、この世界に一人として同じ子どもはおらず、それぞれがみんな特別で、毎回、驚きと発見の繰り返しです。
その中でも敢えて挙げるとすれば、幼児向けコンサートの中で「ボレロ」を演奏した時のことです。15分の演奏時間を5分まで縮めて演奏したのですが、当時演奏してた曲はいつも大体2分程度。果たしてそこまで子供たちの集中力が保てるのか?僕たちにとっては大きな挑戦でした。結果は大成功。演奏中ずっと、子供たちは穏やかな表情で、まるで音の海をふわふわと漂っているようでした。自分の中の既成概念が、一つ崩れ去った瞬間でした。
今年2015年にNPO法人「こどものみかた」を立ち上げられました。設立の経緯を簡単に教えてください。
これまで、オーケストラで演奏することを目標に自分なりに努力し、一流と呼ばれる演奏家の方々の胸を借りながら、本当に有難いことですが、華やかな舞台も数多く経験することができました。そんな中震災が起き、その後演奏家としての自分の無力さを痛感しました。その頃から、演奏家としてどうやって社会と繋がっていくか?ということについて考えるようになり、その活動の基盤としてNPO法人という形態を選びました。
最近はアウトリーチ活動など、こども向けのクラシック音楽の普及啓発活動に取り組む演奏家の方も多くなってきました。そんな中で、こうした子ども向けの企画に本格的に取り組む思いを教えてください。
僕が見てきた偉大な音楽家たちは、子どもたちの前でこそ本気の音楽を響かせていました。自分も、演奏家としていつもそうありたいと思っています。もちろん表現の方法に工夫は必要ですが、相手が子どもだから、大人だからということにとらわれすぎずに、聴く人すべての心に響き渡るような音楽を、できるだけ自由に、素直な心で追求していきたいです。
来年2月に開催する「こどものみかた芸術祭」は、コンサートと造形のワークショップを組み合わせたイベントです。企画の内容を簡単に教えてください。
サン=サーンスの名曲「動物の謝肉祭」をテーマに、コンサートと造形ワークショップが連動したプログラムです。コンサート、ワークショップそれぞれ単独でも参加できますが、併せて参加すると「動物の謝肉祭」の世界により入り込んでいけるはずです。たくさんの動物たちをユーモラスに描きながらも、その裏に風刺やシニカルなジョークを忍ばせ、大人も子どももそれぞれの視点で楽しめる「動物の謝肉祭」の世界の中で、是非親子で感動を共有しあって欲しいと思います。
今後NPO法人「こどものみかた」でこれからやりたいと考えていること、またプロジェクトなどがあれば、ぜひ教えてください。
フィリアホールのような客席とステージの距離が近いホールで、もっと子どものためのプログラムを増やしていきたいです。また、地域の芸術施設が連携したプログラムにも、挑戦したいと考えています。芸術施設が連携して人々にメッセージを発信していくことで、芸術全体が、もっと人々の暮らしと近しいものとして存在する社会を夢見ています。