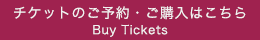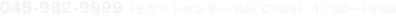秋山和慶(指揮)ロング・インタビューその1
Kazuyoshi Akiyama, conductor
出演日:2018年7月14日(土)14:00
Saturday 14 July 2018 , 14:00
「…ところで今日の指揮者は誰だっけ?」と思われるような、良い演奏会を目指して。
日本を代表する巨匠指揮者のひとり・秋山和慶。その綿密なタクトで国内外オーケストラから大きな信頼を寄せられ、関東では東京交響楽団桂冠指揮者等で年齢を感じさせぬ精力的な活動を続けるマエストロが、この夏に普段はあまり振る機会の多くない小編成オーケストラとフィリアホールに登場します。
「ハーヴェスト室内管弦楽団」、氏に師事した「洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団」のOBを中心とした新しい若きオーケストラの旗揚げ公演となる今回、マエストロにインタビューを行うことができました。充実のロング・インタビュー、2回に分けてお送りいたします。
第1回はオーケストラから「指揮」のお話をご紹介します。
フィリアホールは500席とオーケストラの公演を行うには小さいサイズですが、今回は大変貴重な機会です。
秋山:私がフィリアホールに以前登場したのは20年くらい前かな、小編成のオーケストラで、プーランクのモノ・オペラ「声」を指揮したことがあります。
今年フィリアホールはオープン25周年なので、四半世紀近くですね。その間にずいぶん田園都市線沿線も変わりました。
秋山:青葉台に妹が住んでいましたが、当時は小さい電車一両で中央林間までは走ってなくてね。長津田から少しずつ延びていって、二両から四両となっていき、今の十両編成なんて夢のまた夢だった(笑)。当時は山と畑ばかりで、こんなところに電車走らせてどうするんだろう…って思っていましたが、そんな沿線で文化施設としてフィリアホールは25年。もう長いですね。
今回のオーケストラは、普段はあまりマエストロが振る機会の多くない小編成オーケストラです。あらためて、この「ハーヴェスト室内管弦楽団」が設立された経緯をお伺いできればと思います。
秋山:私が指導している「洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団」の卒業生たちが集まったんです。今はみんな散り散りばらばらで、それぞれ独立して活動している元メンバーたちが、“昔のピシッとしたアンサンブルの夢をもう一度やりたいね”という希望を出してきました。私もそれはいいアイディアだからやろうよ、と言って、会場はどうするか、と考えていたら、幸いにフィリアホールさんが拾って下さった(笑)。こういう団体は、本当にみんなが情熱をかけると思うし、ちょっとでも長続きするような活動が出来ればといいなというのがみんなの夢でもあるんです。
オーケストラも色々な発足の形があると思うのですが、現役演奏家の方々が主導的に集まって…というところは多いケースではないと思います。これから一緒に音楽を創っていくという時に、いわゆる「呼ばれて行く」他のプロのオーケストラと比べて違うところ、そしてどこに一番重きを置いて進めていきたいと思っていらっしゃいますか。
秋山:若くて、ある程度腕がしっかりした連中が集まっているはずだから、上からの指示で何とか…というような感じにはしたくないですね。上からお尻ひっぱたいて-アメとムチじゃないけど-、それが棒振りのテクニックだとも言うこともあるけど、そうではなく自発的に、みんなが音楽やりたいって集まっているわけだから、こちらはそのきっかけを拾ってあげて、ヒントを出してあげて、みんなでアイディアを出し、みんなで作り上げるという形をぜひ守っていきたいなと考えています。奏者たちもそう思っていると思うんだよね。
演奏家の自発的なところに任せる、というところがこのオーケストラの特徴になっていくのではないかと。
秋山:そう。「言われればやりますよ」というのではなくてね。もうちょっと音楽的にフレーズ考えようよとか、テンポの運びの具合とかが行き過ぎちゃった時はちょっと修正してあげる、というようなことが指揮者である僕の役目です。
例えばロマン派の大きなオーケストラ作品を演奏するとして、ただ馬鹿でかい音を出せばいいだろう?という間違いも時々あるわけです。フォルティッシモって書いてあっても、全員がフォルティッシモではなく、ある部分はバランス上抑えなくちゃならない。日本でも本当に良いオーケストラはもちろんそこができますが、欧米のオーケストラでは、そういう部分では楽員みんなが曲を十分に知っていて、「もうそんなに振らなくてもいいよ」って言われるぐらいのところがあるわけです。なにしろ自分たちの楽団はもう100年もやってきてるんるんだから、って。
前に(故)若杉弘さんから聞いた話なんですが、若杉さんがケルンのオーケストラの指揮者在任中、ブラームスの交響曲第4番の冒頭で、普通のオケならまず小さく1,2って振って導き出しますが、「それはいらないよ」って真っ先に言われたんだって。とにかく奏者を見渡して、奏者の気持ちが集中した瞬間に、静かに指揮棒を上方に動かせばあとはみんなが自発的に動く。それに彼は「ハッ」っと気付いたって。本当の良いオーケストラっていうのはそこなんだなと。
演奏者が80人も100人もいてフォルティシモで一斉に始まる場合だったら、「せーのッ」っていう指揮者の指示は必要なんです。最初のアインザッツだけでどうぞ、というわけにはいかないから。でもあとはもう、みんな100年、200年と続いてきた楽団の歴史・伝統みたいなものがあるから、パンパンパンって音楽が進められる。リハーサルなんか1回しかない、っていうのも、そういう土台があるからでね。オーケストラ全体にお金が無いから練習少なくして、みたいなことではなくてね(笑)。
今回の曲目は、近代のプロコフィエフ、バロックのバッハ、古典派のベートーヴェンという組み合わせとなっています。この曲目になった狙い、聴きどころなどを教えてください。
秋山:やはりある部分に固まっちゃいけないなという思いがあって、いろんなものを取り上げようと思っています。第1回目だからということもあるんだけど、バロックはバロックのオーケストラ作品だけとか、室内楽はこんなレパートリーで…という風では無く、スタイルを固めずにやっていきたい。
特定の時代・スタイルを志向するわけではなく、色んな作品を取り上げたいと。
秋山:ええ。お客さんも色んなものを聴きたいと思いますし。今日のモダン楽器による演奏は、バロック当時とは使っている楽器が全然違うし、奏法もヴィブラートのかけ方も違う。現代では、モダン奏法で演奏するバロック作品も、古典派作品も認められています。1900年代前半のロマン派が終わる頃から、オーケストラの奏法は基本的にはそちらの方に移ってきているわけですね。
例えばソリストだったら、(パブロ・)カザルスなどは、バッハを非常に詳しく研究した上で、現代奏法におけるバッハ演奏の元祖になったわけです。ヴィブラートもかけるし、強弱もちゃんとつける。バッハのオリジナル楽譜は強弱の記載がなにも無いわけですから、ちょっとかじったような人は、「バッハは何も書いていないんだから、そんなことやってはいけない」なんて言ったりする人がいる。でもそうではなくて、現代に生きている我々が聴いて感動できる音楽を作ることが大切で、それはもちろん道をはずした、しっちゃかめっちゃかなものじゃ困るけれど、例えばヴァイオリンだったらヘンリク・シェリングなどの名人が道を作ってくれているわけです。
現代では、オーケストラもソリストも、「現代の聴衆に何を提示できるか」ということを本当に意識して活動されていますね。その切り口が結果的にさまざまな方向性に向くと思うのですが、その意識は本当に重要なことなのだと思います。聴衆としての立場でも、今聴いて何か発見できるものというものがほしいなと思いながらやはり見ています。それが結果的に、古いものの発見であったり、古い曲を新しい奏法で演奏するという形であったり。いろいろな形があると思うのですが。
秋山:例えば曲がひとつあって、それを富士山に例えるとします。頂上を極めるには、その曲をマスターして自分のものにして、この演奏が富士山だと名前をつけたい。でもね、登山口はひとつじゃない、いくつもある。だから頂上へのアプローチは、今回はこうだけど3年後はこっち、その次は…って、それだっていい。僕たちが先生たちに言われたのはそういうこと、ひとつに決める必要はない。お客さんや評論家によっては、この人が振ったこの曲は、この前はこう振ったのに今回はこんなに違う、けしからん!というふうに言われちゃったりすることがあるわけね。でも、いろんなアプローチをすれば、いろんな解釈があるんです。結局音楽を壊して、何の曲だか分からなかったっていうのではもちろん困りますが…。
(イツァーク・)パールマンとか、(ピンカス・)ズーカーマンとか、協奏曲を何十回も一緒に演奏している方たちがいます。例えばNYやサンフランシスコでは5日間ぶっ通しで同じ曲をやるわけですが、彼らは毎日違う弾き方をする。じゃないと、自分でやっていて面白くないから。自分がヴァイオリン弾くんだったらそれしか考えられないんだから、って。この考え方には大賛成です。メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲でも、1日目はオーソドックスに、2日目は(冒頭のソロを)ものすごくロマンティックにやったり、3日目には始めから非常に軽やかなテンポでとか、向こうの聴衆はそういうのに慣れていて楽しんでいってくれます。
常に新鮮なアイディアをもって弾いているんですね。
秋山:そうです。音楽といっても、元々譜面は記号でしかないわけです、音の高さと音符の長さ、音の強弱。例えばバッハの作品には強弱が書いていなかったから、自分たちで考えてつけなきゃいけないけど、ロマン派でもマーラーとかになると、それぞれのパートに指示したいことが事細かに書いていたりもします。一方でハイドンやモーツァルト、それにベートーヴェンもそうだけど、スコアでいう上から下まで全部一律にフォルテと書いてあって、そのままバンと一斉に音を出したら、メロディが全然聞こえない!とか、そういうことがいっぱいあるわけだよね。シューマンなんかは特にそうですが、フォルティッシモって書いてあったら、聞こえてくるのはトレモロみたいに刻んでいる弦奏者ばっかりで、2管編成でフルートが2本しかないのに、メロディが客席に行ったら何もわからない、という感じになっちゃったり(笑)。そういうバランスは弾くほうが考えて、お客さんにちゃんと伝えられるような演奏をしよう、というのが本来のオーケストラのやり方だと思います。
かつてNYのアメリカン・シンフォニー・オーケストラでストコフスキーの後を継いだんだけど、ストコフスキーはある時期にフリーボウイング(ボウイングを決めないスタイル)だったわけ。そうすると、例えば上げ弓でクレッシェンド、っていうのはナチュラルにできるけど、中には逆で演奏している奏者と弓が交錯していて、結局はまとまった大きなうねりとかふくらみとかニュアンス、表情が出にくいということもあった。そんな時に、ストコフスキーが辞めて僕が指揮者になって、楽員さんにまず言われたのは、「ストコフスキーにはフリーボウイングでやらされたけれど、あなたもそうなの?」っていうから「そうじゃない、ちゃんとボウイングは決めてやるよ」って言ったら、「ワー良かった!」みたいに言われた(笑)。意思のずれがないオーケストラ、自分でこう表現したいんだっていう意識をまとめるのが指揮者の役目だと思っています。
既にここまでのお話でも出ていますが、指揮者をこれだけ長年されている中で、指揮者というのはどのような存在で、どのようにあるべきか、というところを簡単にお伺いできればと思います。
秋山:「…ところで今日の指揮者は誰だっけ?」と思われるぐらい、指揮者の存在が影武者的であってもいいよね、と思っています。それにはもちろん相応の、全部分かってくれていて、それこそアインザッツ出すだけで、或いはちょっと細かい指示だけでいけちゃうようなオーケストラが必要ですがね。いい音がしてたねって帰っていくお客さんが「今日振ってたの、誰だったっけ?」って言うくらいに(笑)。僕の理想はそれなんだけどね。
それはある意味では本当に難しいことですね。
秋山:難しいことです。ついつい頑張りすぎちゃうよね。
聴く側からしても、派手なアクションとかそういう表面的なことよりも、「音楽そのものが見えてきた」という瞬間に立ち会えると、本当にいいコンサートを聴いたなと思います。
(協力:ハーヴェスト室内管弦楽団)